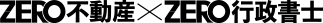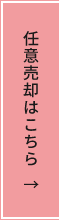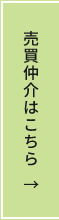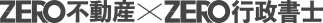都市の中に突然現れる畑や田んぼの中には「生産緑地」として指定されている土地が少なくありません。
この記事では、「生産緑地」について解説していきます。
1.「生産緑地地区」とは
生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地の緑地機能を生かし、計画的に保全することによって豊かな都市環境の形成に資することを
目的として定めるものです。
2.生産緑地に指定されるのはどのような農地か
①現に農業に適正に利用されていること。
②良好な生活環境に相当の効用があること。
③公共施設等の敷地に適している土地であろこと。
④500㎡以上の「一団のものの区域」であること。
注1:条例により300㎡以上に引き下げが可能です。
注2:隣地等とあわせて(他の所有者の農地と合わせることも可)500㎡(条例により300㎡)以上であれば
「一団のものの区域」として指定対象になります。
⑤用排水その他の状況から農業等の継続が可能な条件を備えていること。
3.生産緑地地区に指定された場合
①税制上の優遇措置を受けることができます。
(1)固定資産税が農地評価・農地課税となります。
(2)相続税・贈与税について一定価格を超える部分の納税猶予が受けられる
注:一定の条件に該当した場合は納税が免除されます。
②農地として管理することが義務付けられ、原則農地以外の利用ができません。
注:この義務の期間は、生産緑地の指定から30年間、または所有者の終身です。
(1)原則として、建築や宅地造成等の土地の形質の変更等はできません。
(2)ただし
・その生産緑地において農業等を営むために必要な施設等(農業用倉庫など)
・その生産緑地における農業の安定的な継続に貢献する施設等(農家レストランなど)
は、市町村長の許可を得て、建築等を行うことができます。
4.生産緑地指定の解除の条件
①生産緑地地区の指定から30年経過後。
②生産緑地における「主たる農業従事者」が死亡した場合。
③生産緑地における「主たる農業従事者」が農業等に従事することが不可能な故障が生じた場合。
5.生産緑地指定解除の手続き
4の条件が生じた場合、買取の申出という手続きを経て行われます。
6.まとめ
ここまで、生産緑地制度の概要についてご説明してきました。
市街化区域に農地を所有されている方は、今後その農地をどのように維持・活用されいくかの参考になればと思います。
【筆者】
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
この記事では、「生産緑地」について解説していきます。
1.「生産緑地地区」とは
生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地の緑地機能を生かし、計画的に保全することによって豊かな都市環境の形成に資することを
目的として定めるものです。
2.生産緑地に指定されるのはどのような農地か
①現に農業に適正に利用されていること。
②良好な生活環境に相当の効用があること。
③公共施設等の敷地に適している土地であろこと。
④500㎡以上の「一団のものの区域」であること。
注1:条例により300㎡以上に引き下げが可能です。
注2:隣地等とあわせて(他の所有者の農地と合わせることも可)500㎡(条例により300㎡)以上であれば
「一団のものの区域」として指定対象になります。
⑤用排水その他の状況から農業等の継続が可能な条件を備えていること。
3.生産緑地地区に指定された場合
①税制上の優遇措置を受けることができます。
(1)固定資産税が農地評価・農地課税となります。
(2)相続税・贈与税について一定価格を超える部分の納税猶予が受けられる
注:一定の条件に該当した場合は納税が免除されます。
②農地として管理することが義務付けられ、原則農地以外の利用ができません。
注:この義務の期間は、生産緑地の指定から30年間、または所有者の終身です。
(1)原則として、建築や宅地造成等の土地の形質の変更等はできません。
(2)ただし
・その生産緑地において農業等を営むために必要な施設等(農業用倉庫など)
・その生産緑地における農業の安定的な継続に貢献する施設等(農家レストランなど)
は、市町村長の許可を得て、建築等を行うことができます。
4.生産緑地指定の解除の条件
①生産緑地地区の指定から30年経過後。
②生産緑地における「主たる農業従事者」が死亡した場合。
③生産緑地における「主たる農業従事者」が農業等に従事することが不可能な故障が生じた場合。
5.生産緑地指定解除の手続き
4の条件が生じた場合、買取の申出という手続きを経て行われます。
6.まとめ
ここまで、生産緑地制度の概要についてご説明してきました。
市街化区域に農地を所有されている方は、今後その農地をどのように維持・活用されいくかの参考になればと思います。
【筆者】
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞