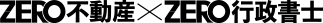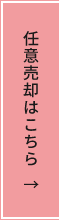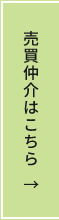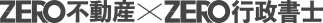こんにちは。今回は、「相続」の手続きの過程における「相続人」についての概要をご説明します。
●相続人について
相続人になることがでるのは誰でしょうか。民法では、相続が開始したときに相続する権利がある「法定相続人」が定められています。
・法定相続人
①配偶者⇒常に相続人となります。婚姻届を出している必要があり、婚姻関係のない内縁の夫、妻や愛人には相続権がありません。
②子⇒第1順位。原則として実子、養子は問いませんし、胎児も既に生まれているものとして相続権があります。また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子といいます)にも相続権があります。(父親の相続の場合は認知が必要)
③直系尊属⇒第2順位。「尊属」とは、いわゆる縦の並びで自分より上の世代に属する親族のことで、両親、祖父母、曽祖父母などを指します。養父母も尊属に含まれます。
子がいない場合や、子全員が相続放棄した場合などには、父母が相続人になり、父母が亡くなる等でいない場合は祖父母がということになりますが、親等の異なる者の間では親等の近い者を先にする規定になっているので、実親が亡くなっていた場合に、養親と祖父母がいる場合には養親が相続人になります。
※「親等」とは
(例)1親等⇒父母、子ども。2親等⇒祖父母、兄弟姉妹。3親等⇒曽祖父母、おじ、おば、甥、姪
④兄弟姉妹⇒第3順位。子や直系尊属がいないときや相続放棄したときなどには、兄弟姉妹が相続人となります。
●「相続人の確定」とは
相続人を確定させるためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍を遡ることで相続人を確定させます。
具体的には、被相続人の出生時の戸籍から死亡までの戸籍(除籍を含む)を取得し、相続人の現在の戸籍を取得することで相続人を把握します。
戸籍の証明書には、「戸籍謄本」・「戸籍抄本」・「除籍謄本」などがあります。
①「戸籍謄本」⇒個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などの記録で、戸籍に記録されている全員の情報を写したものをいいます。
②「戸籍抄本」⇒戸籍謄本の一部を抜き出したもので、戸籍に記載されている一部の人の情報をいいます。
③「除籍謄本」⇒戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などで全員除籍された場合や、他の市区町村に戸籍を移す(転籍)ことにより、戸籍全部が消除された戸籍簿を「除籍簿」といい、除籍簿に記録されている全員について証明したものをいいます。
●まとめ
今回は誰が相続人になれるのかや相続人の調べ方の概要についてご説明しました。基本的には戸籍を調べれば相続人を確定することができますが、事例によっては専門知識が必要な場合や、昔の戸籍で難解な文を読み込まなければいけない場合があります。また、戸籍で相続人を把握できたとしても、相続放棄している場合は、はじめから相続人でなかったものとみなされるため、相続人および相続の順位が変わってしまうこともあり、相続放棄の有無の確認も必要な場合があります。また、相続人を一人でも見落としていた場合、その後の遺産分割協議などが無効になる場合もあるため、相続人の把握は確実に行わなければいけません。不明な点や不安な点があれば、専門職に依頼することも検討されみてはいかがでしょうか。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
●相続人について
相続人になることがでるのは誰でしょうか。民法では、相続が開始したときに相続する権利がある「法定相続人」が定められています。
・法定相続人
①配偶者⇒常に相続人となります。婚姻届を出している必要があり、婚姻関係のない内縁の夫、妻や愛人には相続権がありません。
②子⇒第1順位。原則として実子、養子は問いませんし、胎児も既に生まれているものとして相続権があります。また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子といいます)にも相続権があります。(父親の相続の場合は認知が必要)
③直系尊属⇒第2順位。「尊属」とは、いわゆる縦の並びで自分より上の世代に属する親族のことで、両親、祖父母、曽祖父母などを指します。養父母も尊属に含まれます。
子がいない場合や、子全員が相続放棄した場合などには、父母が相続人になり、父母が亡くなる等でいない場合は祖父母がということになりますが、親等の異なる者の間では親等の近い者を先にする規定になっているので、実親が亡くなっていた場合に、養親と祖父母がいる場合には養親が相続人になります。
※「親等」とは
(例)1親等⇒父母、子ども。2親等⇒祖父母、兄弟姉妹。3親等⇒曽祖父母、おじ、おば、甥、姪
④兄弟姉妹⇒第3順位。子や直系尊属がいないときや相続放棄したときなどには、兄弟姉妹が相続人となります。
●「相続人の確定」とは
相続人を確定させるためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍を遡ることで相続人を確定させます。
具体的には、被相続人の出生時の戸籍から死亡までの戸籍(除籍を含む)を取得し、相続人の現在の戸籍を取得することで相続人を把握します。
戸籍の証明書には、「戸籍謄本」・「戸籍抄本」・「除籍謄本」などがあります。
①「戸籍謄本」⇒個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などの記録で、戸籍に記録されている全員の情報を写したものをいいます。
②「戸籍抄本」⇒戸籍謄本の一部を抜き出したもので、戸籍に記載されている一部の人の情報をいいます。
③「除籍謄本」⇒戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などで全員除籍された場合や、他の市区町村に戸籍を移す(転籍)ことにより、戸籍全部が消除された戸籍簿を「除籍簿」といい、除籍簿に記録されている全員について証明したものをいいます。
●まとめ
今回は誰が相続人になれるのかや相続人の調べ方の概要についてご説明しました。基本的には戸籍を調べれば相続人を確定することができますが、事例によっては専門知識が必要な場合や、昔の戸籍で難解な文を読み込まなければいけない場合があります。また、戸籍で相続人を把握できたとしても、相続放棄している場合は、はじめから相続人でなかったものとみなされるため、相続人および相続の順位が変わってしまうこともあり、相続放棄の有無の確認も必要な場合があります。また、相続人を一人でも見落としていた場合、その後の遺産分割協議などが無効になる場合もあるため、相続人の把握は確実に行わなければいけません。不明な点や不安な点があれば、専門職に依頼することも検討されみてはいかがでしょうか。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞