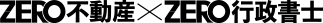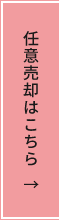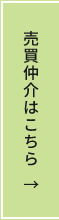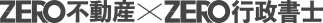こんにちは。前回は、「相続人」についての概要をご説明しました。今回は、相続人が確定したあとの相続の手続きについて引き続き概要をご説明します。
●相続財産について
「相続人」が確定したら次は「相続財産」を確定します。
「相続財産」とは、亡くなった方が残した財産のうち相続人に引き継がれるものです。不動産や現金、預貯金、有価証券をはじめ、賃貸人や賃借人としての地位や権利なども相続財産になる場合があります。また、借金などのマイナスの財産も相続財産になります。
逆に、「相続財産」にならないものとして、亡くなった方の一身に専属し、他人が取得または行使することのできない権利である「一身専属権」があります。具体的には、生活保護受給権や年金受給権などがあります。
他に、相続人等の固有の権利である生命保険金や死亡退職金も相続財産にはなりませんし、お墓や仏壇なども「祭祀財産」として「相続財産」とは区別され、祭祀を主宰するものが承継します。ただし、生命保険金や死亡退職金などは、相続税では「みなし相続財産」として課税財産になりますので注意が必要です。
このような「相続財産」を確定させるためには、どの「相続財産」がどれくらいあるかを調査しなくてはいけません。調査の方法としては、
・家の中を探す。
自宅の金庫や引き出し、棚や仏壇などに金融機関などからの郵便物や通帳などの「相続財産」に関する資料があるかもしれません。
・預貯金や株式などについては、金融機関や証券会社などに問い合わせます。
・貸金庫を契約している形跡があれば、貸金庫内に大切な書類や現金などが残っている可能性があるので、貸金庫も調べます。
・不動産を調べる場合には、法務局や役所で登記事項証明書や名寄帳などの資料を集めます。
・暗号資産や電子マネーなども「相続財産」になりますのでパソコンや携帯電話などのデジタル機器も調べる必要があります。
上記のように、「相続財産」が確定したら、その財産を相続するかどうかを決めます。民法では、相続をするかどうかについて相続人に選択権を認めています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、
・単純承認⇒相続財産を負債を含めて全面的に承継する。
・限定承認⇒相続した資産の範囲内で債務などの責任を負う。
・相続放棄⇒財産の承継を全面的に拒否する。
のいずれかを選択できます。
3ヶ月以内に、上記内容の手続きをしなかった場合には単純承認をしたものとみなされます。また、相続財産の全部や一部を処分したときも単純承認をしたものとみなされます。
●まとめ
今回は、主に相続財産についてご説明しました。相続財産の範囲を確定していないと、遺産分割協議が進められません。しかし、相続財産の調査資料を揃えるなどの作業は専門的な知識を要するなど煩雑な場合もあります。不安な場合には、専門家への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
●相続財産について
「相続人」が確定したら次は「相続財産」を確定します。
「相続財産」とは、亡くなった方が残した財産のうち相続人に引き継がれるものです。不動産や現金、預貯金、有価証券をはじめ、賃貸人や賃借人としての地位や権利なども相続財産になる場合があります。また、借金などのマイナスの財産も相続財産になります。
逆に、「相続財産」にならないものとして、亡くなった方の一身に専属し、他人が取得または行使することのできない権利である「一身専属権」があります。具体的には、生活保護受給権や年金受給権などがあります。
他に、相続人等の固有の権利である生命保険金や死亡退職金も相続財産にはなりませんし、お墓や仏壇なども「祭祀財産」として「相続財産」とは区別され、祭祀を主宰するものが承継します。ただし、生命保険金や死亡退職金などは、相続税では「みなし相続財産」として課税財産になりますので注意が必要です。
このような「相続財産」を確定させるためには、どの「相続財産」がどれくらいあるかを調査しなくてはいけません。調査の方法としては、
・家の中を探す。
自宅の金庫や引き出し、棚や仏壇などに金融機関などからの郵便物や通帳などの「相続財産」に関する資料があるかもしれません。
・預貯金や株式などについては、金融機関や証券会社などに問い合わせます。
・貸金庫を契約している形跡があれば、貸金庫内に大切な書類や現金などが残っている可能性があるので、貸金庫も調べます。
・不動産を調べる場合には、法務局や役所で登記事項証明書や名寄帳などの資料を集めます。
・暗号資産や電子マネーなども「相続財産」になりますのでパソコンや携帯電話などのデジタル機器も調べる必要があります。
上記のように、「相続財産」が確定したら、その財産を相続するかどうかを決めます。民法では、相続をするかどうかについて相続人に選択権を認めています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、
・単純承認⇒相続財産を負債を含めて全面的に承継する。
・限定承認⇒相続した資産の範囲内で債務などの責任を負う。
・相続放棄⇒財産の承継を全面的に拒否する。
のいずれかを選択できます。
3ヶ月以内に、上記内容の手続きをしなかった場合には単純承認をしたものとみなされます。また、相続財産の全部や一部を処分したときも単純承認をしたものとみなされます。
●まとめ
今回は、主に相続財産についてご説明しました。相続財産の範囲を確定していないと、遺産分割協議が進められません。しかし、相続財産の調査資料を揃えるなどの作業は専門的な知識を要するなど煩雑な場合もあります。不安な場合には、専門家への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞